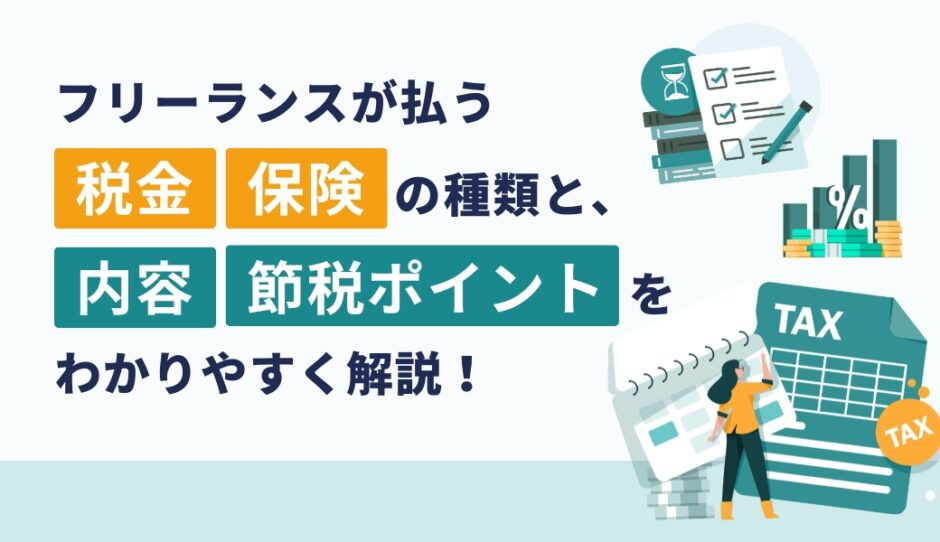フリーランスは税金との付き合いが重要です。
フリーランスになると、会社員時代にはなかった税金の種類や申告・納付の方法を自分で理解し、管理する必要が出てきます。会社員のときと違って、税金の種類や内容を知らないと損する可能性も。
つい支払いすぎることが心配になりがちですが、支払い義務があるものをスルーしてしまった際のペナルティについても、知っておかなくてはいけません。
この記事では、フリーランスが関わる主な税金とその内容をわかりやすく解説します。
フリーランスが関わる主な税金・保険の種類【一覧表あり】

フリーランスが自己管理すべき税金の種類は、以下の通りです。
それぞれどんな税なのか、いつ支払うものなのかなど、しっかり把握しておきましょう。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税(事業によって必要)
- 消費税(事業によって必要)
- 国民健康保険
- 国民年金
国民健康保険と国民年金は税金ではありませんが、支払う必要のある保険なので、まとめてご説明します。
それぞれの対象条件や納付時期、管轄などを、一覧表にまとめました。
次の項目で詳細を記載するので、ここでは自分に関係のある税金はどれか、ざっくり見ておきましょう。
| 税金の種類 | 対象となる収入や条件 | 納付時期・方法 | 管轄 | 備考 |
| 所得税 | 1年間の所得に対して課税 | 確定申告により2月16日~3月15日まで | 税務署(国税庁) | 青色申告で節税可能 |
| 住民税 | 前年の所得に応じて金額が決まる | 毎年6月頃に通知が届き納付 | 住んでいる市区町村 | 一括払いか四括払い |
| 個人事業税 | 課税対象業種かつ、所得が290万円以上 | 8月頃に納付通知が届く | 都道府県税事務所 | |
| 消費税 | 前々年の課税売上が1,000万円を超えると課税 | 翌年3月末までに申告・納付 | 税務署(国税庁) | インボイス制度で免税事業者でも注意が必要 |
| 国民健康保険 | 所得に応じた保険料 | 毎年6月中旬頃に納付書が届く | 住んでいる市区町村 | 口座振替も可能 |
| 国民年金 | 原則20歳以上60歳未満の全員が対象 | 毎年4月に納付書が届く | 日本年金機構 | 口座振替やクレカ払い、電子決済も可能 |
各税金の内容と納税方法を詳しく解説

ここでは、紹介した6種類の税金・保険について、内容と納税方法を詳しくご紹介します。
所得税は、フリーランスが1年間に得た「所得」に対してかかる税金です。
売上から経費・控除を引いた「所得」に応じて、5%~45%の累進課税が適用されます。
年に1回、確定申告(2/16~3/15頃)で計算されて、その年の所得税が定まります。
支払いは銀行やオンライン、振替口座などで可能です。
住民税は前年の所得に応じて、住んでいる都道府県・市区町村に支払う税金です。
会社員は、給料から天引きされる「特別徴収」が可能な場合も多いですが、フリーランスの人は自分で納める「普通徴収」の方法で納税します。
確定申告をもとに、6月頃に自治体から納付書が届きます。
年4回に分けて納付するか、1年分を一括払いすることも可能です。
個人事業税は、フリーランス全員に関わる税金ではありません。「事業所得」が年間290万円超の場合に発生します。
業種により税率は異なりますが、原則5%です。
こちらも確定申告の内容をもとに、8月頃に自治体から納付書が届きます。
消費税とは、売上に対して顧客から預かった消費税を、国に納めるという税金です。
日頃から買い物で支払っていることが多いですが、フリーランスも一定の条件を満たすと、納税義務者になります。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になり、納税義務が発生します。
ちなみに2023年から始まったインボイス制度によって、取引先から「消費税をちゃんと納めている人(課税事業者)」であることを求められるケースが増えました。(免税事業者との取引を避ける企業もあるため)
そのためインボイス制度の影響で、本来は1000万超という条件はあるものの、取引先の都合などで自ら課税事業者になるというケースもあります。
税金ではありませんが、フリーランスが払うべき保険料です。
フリーランスは会社の健康保険に入れないため、各市区町村の「国民健康保険」に加入します。
毎年6月頃に前年の所得に応じた保険料が決定し、納付書が届きます。
その後は納付書の支払期限に従い、年8〜10回程度に分けて支払うこととなります。
自治体によっては、口座振替やクレジット払いも可能です。
国民年金も税金ではなく保険で、老後の年金や障害年金を受け取るための基礎年金制度です。
フリーランスは「第1号被保険者」として加入が義務付けられています。
毎月定額を支払うこととなり、支払い方は納付書、口座振替、クレジットカード払いなどが選べます。
税金の支払いスケジュール(所得税・住民税・消費税)
フリーランスとして働く場合、会社員と違い税金は自分で申告・納付する必要があります。税金の種類ごとに支払い時期が異なるため、年間スケジュールを把握しておくことが重要です。
■所得税(国税)
所得税は1年間(1月1日〜12月31日)の所得をもとに計算され、翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に申告・納付します。
また、前年の所得が一定以上ある場合は「予定納税」が発生し、7月・11月頃に前払いが必要になります。急に大きな支払いが発生しないよう、売上の中からあらかじめ税金分を確保しておくことが大切です。
■住民税(地方税)
住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月頃から支払いが始まります。多くの場合、年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付します。
所得税と違い、住民税は「後から請求が届く」ため、初年度は特に資金繰りに注意が必要です。
■消費税
消費税は、原則として2年前の売上が1,000万円を超えると課税事業者となり、納税義務が発生します(インボイス制度の登録状況によっても異なります)。
消費税の申告・納付は、原則として翌年の確定申告期間中に行います。売上に含まれている消費税を使ってしまうと納税時に資金不足になるため、「預かっているお金」として別管理することが重要です。
フリーランス税金の計算と確定申告のポイント

フリーランスの税金は、「売上」ではなく「所得(利益)」をもとに計算されます。まずは基本的な仕組みを理解しておきましょう。
所得は以下の式で求めます。
売上 − 経費 = 所得
ここからさらに各種控除(基礎控除、社会保険料控除、青色申告特別控除など)を差し引いた金額が「課税所得」となり、その金額に応じて税率が決まります。
つまり、経費や控除を正しく計上することが税負担を抑えるポイントになります。
1年間の売上・経費をまとめる
↓
会計ソフトなどで所得を計算
↓
確定申告書を作成
↓
e-Taxまたは税務署で提出
現在はe-Taxによるオンライン申告が主流で、自宅から手続きが可能です。
フリーランスの税金計算は一見難しく感じますが、「売上 − 経費 = 所得」という基本を理解すれば、仕組み自体はシンプルです。
早い段階で会計管理の習慣をつけることが、税金への不安を減らし、安定した事業運営につながります。
フリーランスなら知っておきたい節税のポイント
フリーランスとして働く以上、「できるだけ手元に残るお金を増やしたい」と考えるのは当然のこと。そのために欠かせないのが節税対策です。
節税とは、法律の範囲内で納める税金を少なくする工夫のこと。脱税とは異なり、正しく知っておくことで毎年の納税額を大きく抑えられる可能性があります。
ここでは、フリーランスが押さえておきたい節税の基本ポイントを3つご紹介します。
■経費を正しく計上する
フリーランスの大きな強みのひとつが「経費として計上できる範囲が広い」ことです。
仕事に必要な支出であれば、スマホ代や交通費、事務用品、カフェでの打ち合わせ費用まで経費にできます。
経費をしっかり記録し、確定申告で正確に計上することで、課税所得(=税金の計算の元になる所得)を減らせるため、結果的に納税額を抑えられます。
■青色申告で控除を最大限に活用する
フリーランスの確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、節税を意識するなら青色申告を選びましょう。
申請方法によって、最大で65万円の所得控除が受けられます。
■小規模企業共済やiDeCoを活用する
将来のための積立をしながら、今の節税にもなる制度が「小規模企業共済」や「iDeCo(個人型確定拠出年金)」です。
例えばiDecoであれば毎月の掛金が「所得控除」として扱われるため、課税される所得が減ります。
特にフリーランスは退職金制度がないため、こうした制度を活用することで、将来への備えと節税を両立できます。
税金を納めないとどうなる?ペナルティとリスク
税金は、払わなければバレないものではありません。
フリーランスとして活動している以上、税務署はあなたの収入を把握する手段を持っています。意図的であっても、うっかりであっても、税金を納めないことには重大なペナルティが発生します。
ここでは、確定申告や納税を怠った場合に起こりうるリスクを具体的に解説します。
■無申告加算税・延滞税が課される
確定申告を忘れていた、または遅れてしまった場合、通常の税金に加え無申告加算税(最大20%)や延滞税(年7.3%など)が発生します。税金を納める金額が大きい場合、数万円〜数十万円のペナルティになることも。
仮に10万円の税金を納め忘れた場合でも、1〜2万円程度の追加負担になる可能性があります。
■税務調査の対象になる
申告漏れや不自然な経費処理があると、税務署から目をつけられることもあります。税務調査が入ると、過去数年分の帳簿やレシートの提出を求められ、細かくチェックされます。
正当な経費でも証拠がなかったり、説明が曖昧だったりすると、否認されて追加課税されることも。
■信用情報に傷がつく可能性も
税金の滞納が長期化した場合、差し押さえや督促が行われることがあり、これが事業者としての信用にも影響します。
将来的に融資を受けたい時や、法人化を検討する場面でもマイナスに働く可能性があります。
■悪質な場合は「脱税」として刑事罰の対象に
特に意図的に売上を隠す、架空の経費を計上するなどの行為は、脱税(刑事罰)として処罰対象になります。
過去にはフリーランスやインフルエンサーが脱税で書類送検された事例もあり、社会的信用を大きく失う結果にもつながります。
まとめ
フリーランスが納める税金は、所得税・住民税・消費税など複数あります。
「税金を自分で支払う」と考えると、難しいイメージがあるかもしれませんが、現在はマイナンバーで管理されていることもあり、届いた通知書・納付書に則って支払えばOKです。
節税ができるポイントになるのは、毎年年明けに行うこととなる確定申告。
それ以外の時期は、「既に決まった額を期日まで支払う」というのが基本となります。そのため、できる限り節税したいという場合は、確定申告を丁寧に行うことが重要です。
今回紹介した税金の種類と申告・納付のポイントを押さえておけば、税務対応への不安も大きく軽減できるでしょう。
節税対策についても学習し、最適な手続きができるようにしてくださいね。